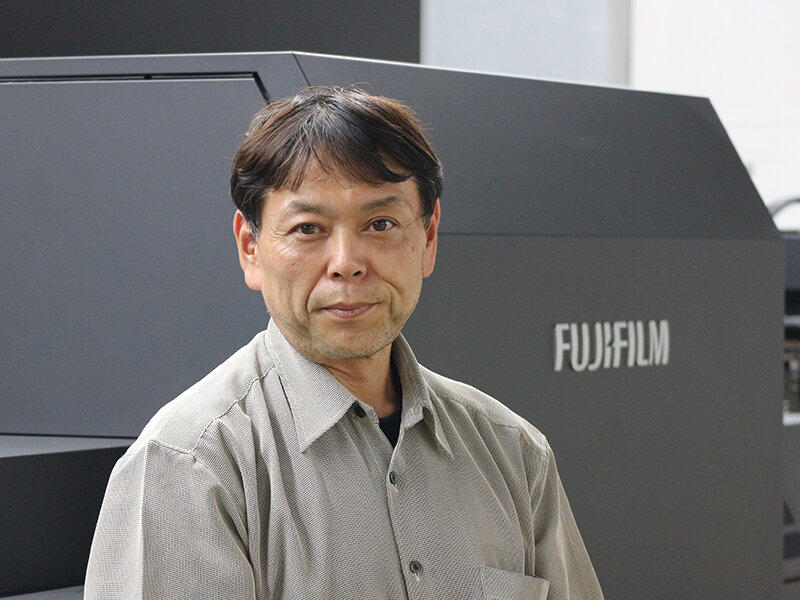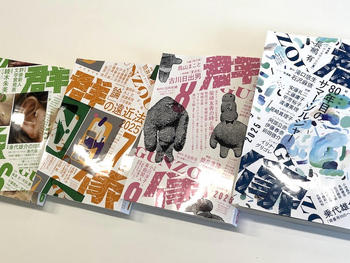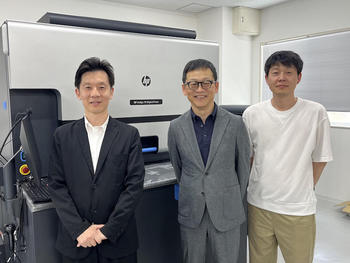食品用器具及び容器包装の規制に関する検討会の取りまとめ
厚生労働省では、平成28年8月より「食品用器具及び容器包装の規制に関する検討会」を開催し、国際的な整合性を含め、食品用器具及び容器包装の安全性を高める具体的な仕組みについて検討を行ってきました。これまでの議論やパブリックコメントを踏まえ、取りまとめが行われました(厚生労働省)
包装材料の大部分は、食品用途に使用されています。その安全性は重要であり、包装材料の製造にあたっては、十分理解しておかなければなりません。
検討の背景
これまで、我が国の食品用器具及び容器包装の規制は、国が規格基準を定めた物質についての使用制限(ネガティブリスト制度:NL)等と、業界団体の自主管理等の取組によって、安全性の確保が図られてきた。
しかしながら、現在のネガティブリスト制度による規制では、欧米等で使用が禁止されている物質であっても、個別に規格基準を定めない限り、直ちに規制することができない。
欧米では、安全性を評価し、使用が認められた物質以外は使用を原則禁止するという仕組み(ポジティブリスト制度:PL)が導入されている。
近年の製品の多様化・輸入品の増加等や、国際的な整合性を踏まえ、新たな制度設計の検討が必要であることから、検討会において議論を行うこととした。
検討会では関係者のヒアリング等を行いつつ議論を行い、これまでの議論について取りまとめとして整理した。
制度のあり方
目指すべき方向性
業界団体の非会員も含めた共通ルールの必要性と、国際的な整合性を図る必要性があることから、リスクを評価し、使用を認めることとした物質以外は原則使用を禁止する制度(ポジティブリスト制度:PL)を基本とする。
具体的な枠組み
制度の対象となる材質:合成樹脂(軟包装、トレイ、プラスチック容器などが対象、OPP, PET, ON, PE, CPPフィルム、PSシート、CPPシートなど)
※金属・紙等の合成樹脂以外の材質は、引き続き必要性や優先度を検討。
リスク管理の方法等
制度の対象となる物質の範囲、リスク管理の方法:国内や諸外国の状況を踏まえ引き続き検討
制度の対象範囲:食品接触部分
※多層品の食品接触部分以外の層については溶出・浸出し食品に混和するおそれがある場合は対象
リスク評価:合理的で科学的な、かつ国際的な整合性を考慮した手法の早急な確立が必要
その他:既存物質は、一定の要件を満たす場合には、引き続き使用可。重金属等の毒性が顕著な物質、不純物等は、これまでと同じリスク管理方法を維持
事業者間の情報伝達
器具及び容器包装の製造事業者:ポジティブリストに適合した原材料であることを確認(製造管理の一環)
原材料の製造事業者:器具及び容器包装の製造事業者の求めに応じ、適切な情報を提供
器具及び容器包装の販売事業者・食品製造事業者:器具及び容器包装の製造事業者から販売事業者等に対し、必要な情報を提供
適正な製造管理
器具及び容器包装の製造事業者に適正な製造管理(GMP)を行うことを制度として位置付け。
包装材料の印刷、ラミネート、製袋、成型(真空成型・射出成型)の加工現場は対象となる。体制を整えなければならない。
事業者の把握・地方自治体の監視指導
器具及び容器包装の製造事業者の把握のため、届出等の仕組みを検討
監視指導については、まずは、事業者の把握、製造管理の状況の把握等を行うことが必要。
以上であるが、補足説明をすると、これまで我が国の食品に用いられる器具及び容器包装(以下「器具及び容器包装」という)については、国が食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づき規格基準を定めた物質についての使用の制限等に加え、業界の自主管理等の取組によって製品の安全性が守られてきた。具体的な規制内容については厚生省告示370号として業界では知られている。
欧米等では、合成樹脂等の器具及び容器包装について、安全性を評価し、使用を認められた物質以外は使用を原則禁止するという仕組み(ポジティブリスト制度:PL)による管理が、国の制度として導入されている。また、アジア諸国においても、ポジティブリスト制度による管理について、導入又は導入に向けた検討が進められている。中国は導入済み。
国内で受注・発注・製造した包材で食品を包装し、その包装食品が海外に輸出されたとき、現地のPLに適合していないと流通できなく、全品回収となる。損害が発生する。これまで厚生労働省において国内外の知見や技術進歩等に関する調査・検討が行われており、平成27年6月には「食品用器具及び容器包装の規制のあり方に係る検討会」における検討についての中間取りまとめが公表されている。
新着トピックス
2025年10月1日製品・テクノロジー
産業⽤インクジェットプリンタ、カッティングプロッタ、3Dプリンタを手掛ける(株)ミマキエンジニアリング(本社/長野県東御市、池田和明社長)は今年4月、同社初のUV-DTF(UV硬化式...全文を読む
2025年9月30日製品・テクノロジースペシャリスト
最速900メートル/分の超高速印刷が可能なPROSPERヘッドは、日本でもDM市場を中心に数百台が稼働しているが、コダックジャパン・プリント事業部デジタルプリンティング営業本部の河原...全文を読む
最新ニュース
SCREEN、京都芸大・月桂冠と産学連携 - 学生デザインラベルの日本酒商品化
2025年10月8日
京都市立芸術大学(以下「京都芸大」)、月桂冠(株)、(株)SCREENグラフィックソリューションズ(以下「SCREEN」)の3者は、産学連携による共同プロジェクトを実施し、京都芸大・...全文を読む
ミマキ、OGBS2025で昇華転写用IJプリンタ「TS200」を国内初披露
2025年10月2日
(株)ミマキエンジニアリング(本社/長野県東御市、池田和明社長)は、9月30日と10月1日に東京・池袋のサンシャインシティにおいて開催されたオーダーグッズビジネスショー(OGBS)2...全文を読む
swissQprint Japan、VIPオープンハウスウィーク-10月28日〜31日
2025年10月1日
swissQprint Japan(株)(本社/横浜市港北区新横浜3-2-6、アドリアーノ・グット社長)は、顧客の要望に応え、最新世代のフラットベッドプリンタを紹介するオープンハウス...全文を読む
連載|より包装材料の印刷の理解を深めるために - 11
伸びるデジタル印刷と包装分野への参入
2018年9月26日スペシャリスト

一般社団法人PODi
1996年に米国で誕生した世界最大のデジタル印刷推進団体。印刷会社800社、ベンダー50社以上が参加し、デジタル印刷を活用した成功事例をはじめ、多くの情報を会員向けに公開している。また、WhatTheyThinkをはじめDMAなどの海外の団体と提携し、その主要なニュースを日本語版で配信している。
食品用器具及び容器包装の規制に関する検討会の取りまとめ
厚生労働省では、平成28年8月より「食品用器具及び容器包装の規制に関する検討会」を開催し、国際的な整合性を含め、食品用器具及び容器包装の安全性を高める具体的な仕組みについて検討を行ってきました。これまでの議論やパブリックコメントを踏まえ、取りまとめが行われました(厚生労働省)
包装材料の大部分は、食品用途に使用されています。その安全性は重要であり、包装材料の製造にあたっては、十分理解しておかなければなりません。
検討の背景
これまで、我が国の食品用器具及び容器包装の規制は、国が規格基準を定めた物質についての使用制限(ネガティブリスト制度:NL)等と、業界団体の自主管理等の取組によって、安全性の確保が図られてきた。
しかしながら、現在のネガティブリスト制度による規制では、欧米等で使用が禁止されている物質であっても、個別に規格基準を定めない限り、直ちに規制することができない。
欧米では、安全性を評価し、使用が認められた物質以外は使用を原則禁止するという仕組み(ポジティブリスト制度:PL)が導入されている。
近年の製品の多様化・輸入品の増加等や、国際的な整合性を踏まえ、新たな制度設計の検討が必要であることから、検討会において議論を行うこととした。
検討会では関係者のヒアリング等を行いつつ議論を行い、これまでの議論について取りまとめとして整理した。
制度のあり方
目指すべき方向性
業界団体の非会員も含めた共通ルールの必要性と、国際的な整合性を図る必要性があることから、リスクを評価し、使用を認めることとした物質以外は原則使用を禁止する制度(ポジティブリスト制度:PL)を基本とする。
具体的な枠組み
制度の対象となる材質:合成樹脂(軟包装、トレイ、プラスチック容器などが対象、OPP, PET, ON, PE, CPPフィルム、PSシート、CPPシートなど)
※金属・紙等の合成樹脂以外の材質は、引き続き必要性や優先度を検討。
リスク管理の方法等
制度の対象となる物質の範囲、リスク管理の方法:国内や諸外国の状況を踏まえ引き続き検討
制度の対象範囲:食品接触部分
※多層品の食品接触部分以外の層については溶出・浸出し食品に混和するおそれがある場合は対象
リスク評価:合理的で科学的な、かつ国際的な整合性を考慮した手法の早急な確立が必要
その他:既存物質は、一定の要件を満たす場合には、引き続き使用可。重金属等の毒性が顕著な物質、不純物等は、これまでと同じリスク管理方法を維持
事業者間の情報伝達
器具及び容器包装の製造事業者:ポジティブリストに適合した原材料であることを確認(製造管理の一環)
原材料の製造事業者:器具及び容器包装の製造事業者の求めに応じ、適切な情報を提供
器具及び容器包装の販売事業者・食品製造事業者:器具及び容器包装の製造事業者から販売事業者等に対し、必要な情報を提供
適正な製造管理
器具及び容器包装の製造事業者に適正な製造管理(GMP)を行うことを制度として位置付け。
包装材料の印刷、ラミネート、製袋、成型(真空成型・射出成型)の加工現場は対象となる。体制を整えなければならない。
事業者の把握・地方自治体の監視指導
器具及び容器包装の製造事業者の把握のため、届出等の仕組みを検討
監視指導については、まずは、事業者の把握、製造管理の状況の把握等を行うことが必要。
以上であるが、補足説明をすると、これまで我が国の食品に用いられる器具及び容器包装(以下「器具及び容器包装」という)については、国が食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づき規格基準を定めた物質についての使用の制限等に加え、業界の自主管理等の取組によって製品の安全性が守られてきた。具体的な規制内容については厚生省告示370号として業界では知られている。
欧米等では、合成樹脂等の器具及び容器包装について、安全性を評価し、使用を認められた物質以外は使用を原則禁止するという仕組み(ポジティブリスト制度:PL)による管理が、国の制度として導入されている。また、アジア諸国においても、ポジティブリスト制度による管理について、導入又は導入に向けた検討が進められている。中国は導入済み。
国内で受注・発注・製造した包材で食品を包装し、その包装食品が海外に輸出されたとき、現地のPLに適合していないと流通できなく、全品回収となる。損害が発生する。これまで厚生労働省において国内外の知見や技術進歩等に関する調査・検討が行われており、平成27年6月には「食品用器具及び容器包装の規制のあり方に係る検討会」における検討についての中間取りまとめが公表されている。
新着トピックス
-
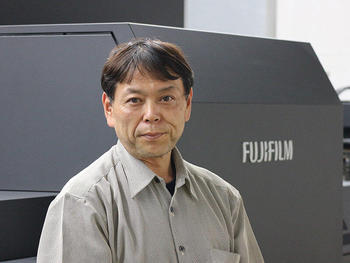 樋口印刷所(大阪)、下請け100%のJet Pressビジネスとは
樋口印刷所(大阪)、下請け100%のJet Pressビジネスとは
2025年10月8日 ケーススタディ
-
 ダイコウラベル、新市場への進出に貢献〜デジタルの強みで顧客メリットを創出
ダイコウラベル、新市場への進出に貢献〜デジタルの強みで顧客メリットを創出
2025年10月7日 ケーススタディ
-
 ミマキ、UV-DTF市場に参入〜プリント形状の課題を解決
ミマキ、UV-DTF市場に参入〜プリント形状の課題を解決
2025年10月1日 製品・テクノロジー
-
 コダック、パッケージ分野で新アプリケーション開拓へ
コダック、パッケージ分野で新アプリケーション開拓へ
2025年9月30日 製品・テクノロジースペシャリスト
-
 青森県コロニー協会、多様性のある職場環境の構築を支援 [インプレミアIS29s導入事例]
青森県コロニー協会、多様性のある職場環境の構築を支援 [インプレミアIS29s導入事例]
2025年9月30日 ケーススタディ
新着ニュース
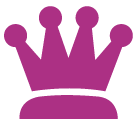 SNSランキング
SNSランキング
- 63shares講談社、フルデジタル書籍生産システムが新たな領域に
- 50sharesリコー、企業内・商用印刷の幅広いニーズに対応するカラー機の新機種発売
- 44shares富士フイルムBI、デジタル印刷ワークフローソフトウェアが「IDEA」ファイナリストに
- 40shares樋口印刷所(大阪)、下請け100%のJet Pressビジネスとは
- 38shares門那シーリング印刷(大阪)、除電機能で作業効率向上[Revoria Press PC1120導入事例]
- 38sharesコニカミノルタジャパン、AccurioDays2025で新たなフラッグシップモデルを公開
- 37sharesSCREEN GAとSCREEN GPJ、「パッケージに彩りを」テーマに「JAPAN PACK 2025」に出展
- 35sharesSCREEN、インクジェット技術を核とした未来のオープンイノベーション拠点開設
- 30sharesコニカミノルタジャパン、機能強化モデル「AccurioPress C7100 ENHANCED」発売
- 28sharesパラシュート、Webプラットフォームをベースとした販促資材管理サービスの提供開始