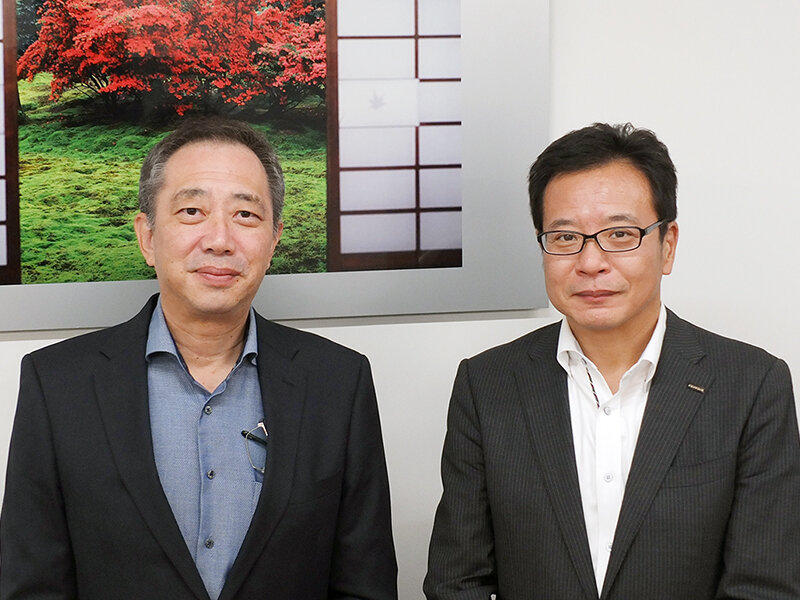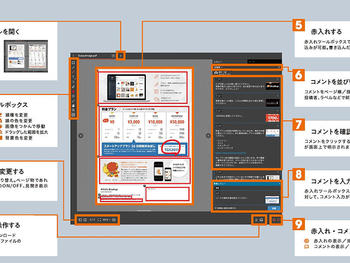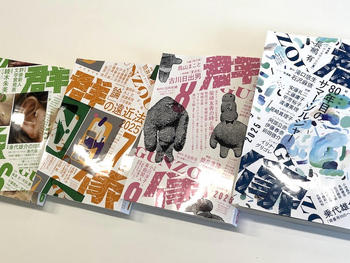マーケターがこれまでとってきたデジタルオンリー戦略との蜜月が終わりつつある。デジタルチャネルへの投資は今後も続くだろうが、印刷メディアが再認識され、メディアミックスの中でますます重要視されてきているからだ。印刷会社が上流のビジネス領域に参入する格好のチャンスが到来したといえよう。
生活者がブランドに接するとき、どのように効果的なオム二チャネル戦略を策定し、展開するか、企業のマーケターを支援する機会が増えていくだろう。この領域で、既に成功している印刷会社3社の専門家にその秘訣を聞いてみた。

印刷業界が、クロスメディアという言葉を使いはじめて久しい。だが、業界を取り巻く環境は複雑になるばかりだ。先陣を切って、この領域でサービスを提供している印刷会社は、企業のマーケターが生活者に伝えるコミュニケーションを、タイムリー、かつレレバント(関連性の高い)なものにするため、見合ったサービスを提供できるよう、自ら事業を磨き続けなくてはならない。新規参入者にとっては、学ぶことが多すぎるため、ハードルが益々高くなっていくであろう。
最近、オム二チャネルサービスで成功しているいくつかの印刷会社と話す機会があり、彼らに成功の秘訣を聞くことができた。秘訣を教えてくれた寛大な印刷会社は以下の通り。
社名:Harland Clarke
役職:チーフ・アーキテクト
名前:Tim Cooper
社名:Curtis 1000
役職:データプロセシングマネージャー
名前:Kevin Neal
社名:Strategic Content Imaging
役職:CTO
名前:Anil Kapoor
本題に入る前に、まず用語の定義づけをしなくてはならない。企業のマーケターのほとんどは、クロスメディアという言葉を聞いてもそれについて知らないという。印刷業界特有の用語だからだ。マルチチャネルとかオム二チャネルといった方がわかり易いかもしれない。
Anil Kapoor氏は、クロスメディア、またはクロスチャネルについて、こう説明する。例えば、生活者がメルマガを受信して、リンクをクリックして、オンラインまたは実店舗に行ったとしよう。企業が生活者に複数のコミュニケーションチャネルを通じて同じ製品について伝えるにもかかわらず、それらが連動していなく、つながりやリンクがまったくない状況が、クロスメディア、またはクロスチャネルだという。
マルチチャネルはどうだろうか。来店した顧客は、クロスチャネルより統合された形で、複数のチャネルをたどって誘導されるが、店舗などの担当者は顧客のエンゲージメントによる購買履歴をまったく把握していない状況を指す。
一方、オム二チャネルでは、すべての糸が絡み合うように、テレビを見ながらタブレットを閲覧したとしても、タブレットを単体で閲覧したとしても一環としたユーザーエクスペリエンスを提供できる状況を指す。ひとつの例として、テレビのスポーツ観戦がある。テレビの実況中継に合わせて、視聴者が自分の好きな選手の成績やプレイをリアルタイムにタブレットで閲覧できるようにすれば、その履歴をトラッキングし、印刷物、オンライン、店舗などで後ほどのユーザーへのコミュニケーションにつなげていくことができる。
新着トピックス
swissQprint、ビジネスの将来的な成長を促進するワイドフォーマットプリンタ
2025年11月25日ケーススタディ
swissQprintのユーザーであるMayfield Press社とPip n Chip社(まったく異なる業種)の2社は、swissQprintのマシンが自社のビジネスニーズに合わ...全文を読む
樋口印刷所(大阪)、下請け100%のJet Pressビジネスとは
2025年10月8日ケーススタディ
「刷り技術集団」として下請けに徹する(有)樋口印刷所(大阪市東住吉区桑津、樋口裕規社長)は、コロナ禍にあった2021年12月、富士フイルムの商業印刷向け枚葉インクジェットデジタルプレ...全文を読む
最新ニュース
トキワ印刷、厚紙仕様のIJデジタルプレス「JetPress750S」導入
2025年12月26日
パッケージおよび厚紙・特殊紙印刷のトキワ印刷(株)(本社/大阪府東大阪市池島町、渡辺貞城社長)はこのほど、富士フイルムの枚葉インクジェットデジタルプレス「JetPress750S」(...全文を読む
2025年12月26日
DICグラフィックス(株)(甲斐敏幸社長)は、デザイン・印刷・マーケティング業務を支援する色見本帳アプリ「DICデジタルカラーガイド」に、業界初の「AI配色検索機能」を搭載した。 ...全文を読む
コダック、自動化や統合性を強化したPRINERGY最新バージョン発表
2025年12月26日
コダックは、PRINERGYソフトウェアの新バージョン11.5を発表した。 PRINERGYプラットフォームは、アナログ印刷とデジタル印刷の両方にわたり、生産を効率化・最適化する統...全文を読む
オム二チャネルコミュニケーション:成功の秘訣とは
2018年8月17日マーケティングスペシャリスト

一般社団法人PODi
1996年に米国で誕生した世界最大のデジタル印刷推進団体。印刷会社800社、ベンダー50社以上が参加し、デジタル印刷を活用した成功事例をはじめ、多くの情報を会員向けに公開している。また、WhatTheyThinkをはじめDMAなどの海外の団体と提携し、その主要なニュースを日本語版で配信している。
マーケターがこれまでとってきたデジタルオンリー戦略との蜜月が終わりつつある。デジタルチャネルへの投資は今後も続くだろうが、印刷メディアが再認識され、メディアミックスの中でますます重要視されてきているからだ。印刷会社が上流のビジネス領域に参入する格好のチャンスが到来したといえよう。
生活者がブランドに接するとき、どのように効果的なオム二チャネル戦略を策定し、展開するか、企業のマーケターを支援する機会が増えていくだろう。この領域で、既に成功している印刷会社3社の専門家にその秘訣を聞いてみた。

印刷業界が、クロスメディアという言葉を使いはじめて久しい。だが、業界を取り巻く環境は複雑になるばかりだ。先陣を切って、この領域でサービスを提供している印刷会社は、企業のマーケターが生活者に伝えるコミュニケーションを、タイムリー、かつレレバント(関連性の高い)なものにするため、見合ったサービスを提供できるよう、自ら事業を磨き続けなくてはならない。新規参入者にとっては、学ぶことが多すぎるため、ハードルが益々高くなっていくであろう。
最近、オム二チャネルサービスで成功しているいくつかの印刷会社と話す機会があり、彼らに成功の秘訣を聞くことができた。秘訣を教えてくれた寛大な印刷会社は以下の通り。
社名:Harland Clarke
役職:チーフ・アーキテクト
名前:Tim Cooper
社名:Curtis 1000
役職:データプロセシングマネージャー
名前:Kevin Neal
社名:Strategic Content Imaging
役職:CTO
名前:Anil Kapoor
本題に入る前に、まず用語の定義づけをしなくてはならない。企業のマーケターのほとんどは、クロスメディアという言葉を聞いてもそれについて知らないという。印刷業界特有の用語だからだ。マルチチャネルとかオム二チャネルといった方がわかり易いかもしれない。
Anil Kapoor氏は、クロスメディア、またはクロスチャネルについて、こう説明する。例えば、生活者がメルマガを受信して、リンクをクリックして、オンラインまたは実店舗に行ったとしよう。企業が生活者に複数のコミュニケーションチャネルを通じて同じ製品について伝えるにもかかわらず、それらが連動していなく、つながりやリンクがまったくない状況が、クロスメディア、またはクロスチャネルだという。
マルチチャネルはどうだろうか。来店した顧客は、クロスチャネルより統合された形で、複数のチャネルをたどって誘導されるが、店舗などの担当者は顧客のエンゲージメントによる購買履歴をまったく把握していない状況を指す。
一方、オム二チャネルでは、すべての糸が絡み合うように、テレビを見ながらタブレットを閲覧したとしても、タブレットを単体で閲覧したとしても一環としたユーザーエクスペリエンスを提供できる状況を指す。ひとつの例として、テレビのスポーツ観戦がある。テレビの実況中継に合わせて、視聴者が自分の好きな選手の成績やプレイをリアルタイムにタブレットで閲覧できるようにすれば、その履歴をトラッキングし、印刷物、オンライン、店舗などで後ほどのユーザーへのコミュニケーションにつなげていくことができる。
新着トピックス
-
 帆風(東京)、デジタル印刷のリードタイム短縮[Revoria XMF PressReady導入事例]
帆風(東京)、デジタル印刷のリードタイム短縮[Revoria XMF PressReady導入事例]
2025年12月26日 ケーススタディ
-
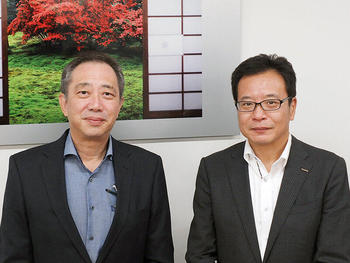 FFGS、機械・材料・サービスを「三位一体」で
FFGS、機械・材料・サービスを「三位一体」で
2025年11月28日 企業・経営
-
 swissQprint、ビジネスの将来的な成長を促進するワイドフォーマットプリンタ
swissQprint、ビジネスの将来的な成長を促進するワイドフォーマットプリンタ
2025年11月25日 ケーススタディ
-
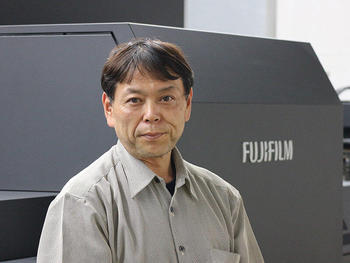 樋口印刷所(大阪)、下請け100%のJet Pressビジネスとは
樋口印刷所(大阪)、下請け100%のJet Pressビジネスとは
2025年10月8日 ケーススタディ
-
 ダイコウラベル、新市場への進出に貢献〜デジタルの強みで顧客メリットを創出
ダイコウラベル、新市場への進出に貢献〜デジタルの強みで顧客メリットを創出
2025年10月7日 ケーススタディ